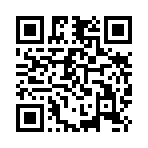2012年01月31日
77 コウベモグラとアズマモグラ 和歌山県内の分布

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2012年1月30日掲載
和歌山県内には大きなアズマモグラの孤立群があります。
紀伊半島独特な地形による、この分布はとても興味深いです。
調査した細田先生のお話では、トンネルの直径が5センチを境に、
大きければコウベモグラ、小さければアズマモグラと判断できるとのことです。
同じ種類でも個体や地域により変異があり、
文献によると、コウベモグラの門歯は円弧状に並ぶと書いてあります。

我が家にあるコウベモグラの頭骨。
門歯の並びはいかがですか?
続いて体の骨格

腰の骨が細い!
上腕骨は短く太い!
モグラは泳いで移動することがあるようで、
貴重なお写真を、松井永喜さん(兵庫県西宮市で撮影)
が、提供してくださいました


鼻をシュノーケルのように使っています!
細田先生も、川はコウベモグラが分布を拡大する障壁にはならない
とおっしゃっていました。
身近でもあまり目にしないモグラ。
次回は、その動きを、飼育展示する多摩動物公園で観察した様子を
ご紹介します!(2月6日掲載予定です)
2012年01月24日
76 竜の名がつく海の動物

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2012年1月23日掲載
干支にちなみ、竜とどこか似ている海の動物2グループを観察しました。
竜蝦とも書く、イセエビ。
立派なエビを見て、どのお客さんも、「おいしそう」と言っていました

エビには2対の触角があると教えていただき、
ニシキエビ(県内では珍しい種類)で、その使い方を観察。

2又に分かれた第1触角と、長い第2触角。
センサーとして、また手のように他の動物をさえぎるのにも使っていました。
一方でこんなエビも!!

セミエビ。 セミのようなエビ。
第2触角が、板状になっている?
触角を見比べるだけで、同じエビでも多様なことを改めて発見しました

もう1つはタツノオトシゴ
この種類はタカクラタツ。

透き通った背びれが見えますか?
体をこすりつけるしぐさも!魚なのに


鱗が板状に変化しています。。
不思議な魚です。
面白くて、両方の水槽を行ったり来たり、
2時間半、見続けていました。
ニシキエビもタツノオトシゴも1頭ずつの展示です。
掲載前にもし、体調が悪くなったらと心配しましたが、今も元気で過ごしています。
タツノオトシゴは、細かいプランクトンを食べ、飼育が難しいそうです。
ぜひ、ご覧になってください

2012年01月18日
75 人を導く神の鳥 熊野の八咫烏

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2012年1月16日掲載
2012年最初の記事は、昨年末に訪れた台風の被災地、熊野那智大社の話題にさせて頂きました。
土石流による甚大な被害を受けられましたが、
那智の瀧そのものは、昔と同じ勢いで神々しく流れ落ち、

神聖な気持ちで階段を登り、心地よい汗をかきながら那智大社に入りました。

熊野三山では同じ神様をお祀りし、
またそれぞれに主神がいらっしゃいます。

熊野那智大社の主神は、夫須美大神さま。
「ふすみ」は「むすび」に通じ、
努力が実を結ぶ 人の縁が結ばれる など、あらゆる幸せが結ばれる
ご利益があります。
被災地の復興に向けて、絆が結ばれることを改めて願いました。
人を導いた八咫烏は、建角身命が姿を変えられたとのこと。その神様も銅像と共に祀られています。

八咫烏が象徴する深い信仰と歴史。
奥深い森と壮大な瀧に囲まれるだけで、心が洗われる気がしました。
3本足の烏は、日本サッカー協会のシンボルマークでもあります。
2月にはなでしこJAPANが、和歌山県で合宿の予定もあります!
ぜひ多くの人に、世界遺産の熊野に来ていただければ幸いです

2012年01月15日
74 台風12号被害時のペット救護

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年12月26日掲載
和歌山県に甚大な被害をもたらした台風12号。
犠牲になられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げ、
被災された方々のご健康と復興を祈念申し上げます。
今もなお、今後の生活再建に向けてご苦労されている被災地の状況に
多くの方が引き続き関心を持ち、支援の輪が広がりますよう、願っております。
紀南での動物の話題を通して、何か発信するお手伝いができればと、
ペット救護の状況を取材させていただきました。
自治体が独自で率先して行われた事例を通して、
被災者のお言葉からも、動物救護が人の心の支えとなり、
さらに人の救護につながることを実感しました。
そして様々な方々の、いろいろなご意見をお聞きし、
行政をはじめとする初動体制のしくみを、今から作る必要性を
皆さんと確認し、文章化できたことが、大きかったと思います。
掲載紙をお送りした後に、被災者の方からお電話を頂き、
「これからも伝えてください」 とおっしゃってくださったことが
何よりもうれしく、ありがたかったです。
どうか被災された皆様、くれぐれもお体をご自愛なさってください。
また伺わせていただきます

2012年01月15日
73 油汚染の水鳥救護講習会

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年12月19日掲載
海上での油汚染事故は、世界で頻繁に起きていて、
油まみれになった鳥の救護ができる人材育成が求められています。
2回の講習を受ければボランティア登録ができるとのこと、
獣医の方々に混じり、講習会に参加しました。
人間も油汚染を受けるので、皮膚を露出しないよう、
ゴーグル、防護服、帽子を装着。
5人1グループで、カモやガチョウ1羽を担当。

長い管を食道に通し、
油を吸着する活性炭液や栄養剤を注入。

熱めのお風呂くらいのお湯に体を沈めると、
カモはおとなしくしていました。
羽を痛めないよう、決してこすらず、
泡立てた水流で洗うのがポイントです。

すすぎ
水をかけているのに、水滴がつぎつぎと背中に!
羽の撥水性に驚きます!!
水辺でくらす水鳥たちの見事な体のしくみ。
だからこそ、海の環境汚染に敏感です。
この記事を見て、2回目の講習会を申し込まれた方がいらっしゃったようで、
関心を持っていただきうれしかったです

2012年01月14日
72 アナグマとタヌキ

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年12月5日掲載
交通事故に遭ったアナグマの遺体があると、
知人が連絡をくれたので、回収に行きました。

この道路では前の年の夏にも、他のアナグマの遺体があり、
周辺の山林にアナグマが多く生息していることを知ると共に、
道路を横切って犠牲になる動物たちを痛ましく思います。
管轄する行政にお聞きすると、交通事故以外のケースもありますが、
犬や猫を除いた、動物の遺体焼却数(鳥を含む)は、232頭(22年度)だったそうです。
せめて標本として価値を残せたらと、回収に行くと、大きくて重い

アナグマがこんなに重いのかと、計測して文献を調べると、
秋に脂肪をたくさん蓄え、春と体重が全然異なることを確認できました。
剥皮に挑戦したら、脂肪が厚く、難儀しました。。
アナグマの肉は美味しいのか、編集担当記者から尋ねられ、
猟友会の方にお聞きしたら、臭みがなく、イノシシの肉の味に似ていて
油がのっていて美味しいそうです

でも今は、肉用として捕獲されるのは少ないようです。
(県のアナグマ捕獲頭数 22年度は30頭のみ)
穴を掘る頑丈な前足、長い爪

アナグマの巣穴

タヌキと混同されたのか、知名度が低いアナグマ。
注目し、おだやかに暮らせるよう見守りたいです

2012年01月14日
71 和歌浦干潟の多様なカニたち

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年11月28日掲載
和歌山大学生物学教室とわかのうらひがた倶楽部主催による干潟の観察会。
2002年から毎年2回、行われています。
バケツを手に長靴姿の親子など、たくさんの参加がありました。

砂浜には無数の小さな穴がぼこぼこと。
生物が絶えず出入りし、干潟が生きている!と実感しました。
またこんなに整然とした砂粒のじゅうたん!

コメツキガニが、砂の表面の有機物を削り取った跡です。
記事では紹介しませんでしたが、こんなカニも。

ガザミ(ワタリガニ)です。
泳ぎが得意で、足が平べったくなっています。(遊泳脚)
カニだけでも多種多様。
実は貝類はもっと多様で、かけがえのない干潟です

2012年01月14日
70 ヤギが草刈りに大活躍!

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年11月21日掲載
県がヤギやウシを耕作放棄地に貸し出す事業を知り、
ちょうど放牧される日に立ち合せていただきました。

すさみ町の畜産試験場からトラックで運ばれてきた
ザーネン種のオス。
動物園でシバヤギなど、小さなヤギを見慣れていたので、
大きい!というのが第一印象でした。
そして温和でおとなしく、人に慣れていました。
電気柵と雨よけの小屋が準備された中に放牧されたところ

それが1ヶ月も経たないうちに

ほとんど食べ尽くしました。
借りた方も、その速さに驚かれ、
また、ヤギに愛着を持たれたそうです

冬はヤギが食べる青々した草があまりないので、春以降の時期が良いそうです。
2012年01月12日
69 記録に残す大切さ 96才現役医師の小川忠宏先生

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年11月7日掲載
外来種のアオマツムシが和歌山県内でいつ確認されたかを、
論文にまとめておられたのが、この小川先生です。
その経緯を教えて頂きに伺いました。
地域の総合医として、今も現役でお仕事をされている小川先生。
最初にお会いしたときは、ベレー帽をかぶりお洒落でいらっしゃり、
お尋ねしたことについて、わかりやすく詳しく、お答えくださいました。
感銘を受けたのは、克明な記録を欠かさずとり、きちんと保管されていることです。
戦前に採取したアオマツムシの標本もあり、保存状態の良さに驚きました。
今は戦地ビルマでの体験記をまとめておられ、
「書けば残るでしょう」というお言葉が、強く印象に残りました。
記録に残す、次の世代に伝える。
改めてその大切さを学ばせていただき、尽力しようと思いました。
2012年01月12日
68 樹上で鳴く緑色のコオロギ アオマツムシ

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年10月31日掲載
樹上で甲高く鳴く外来種、アオマツムシの話題。
いつ頃まで鳴き声が聞こえるか(掲載予定日まで聞こえるか)
少しはらはらしていたのですが、
昨年の11月は暖かかったせいか、11月末まで、聞くことができました

従来のコオロギ類たちの、コロコロリー、とか、チンチロリン などとは、
明らかに違う虫の音です。
それも木の高いところから。
この音声に魅了され、研究し続けておられる小川先生にお会いできたお話は
つぎのコラムで改めてご紹介します。
2012年01月09日
67 双子パンダ タケを食べ始め独り立ち

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年10月24日掲載
希少なジャイアントパンダの繁殖を成功させているアドベンチャーワールド。
現在は8頭ものパンダを飼育展示しています。
いつ行っても、だれかしらが起きていて、食べるところが見られます。
取材よもやま話をご覧ください。
2012年01月08日
66 ウミガメ調査パトロール

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年10月17日掲載
ウミガメになかなか出会えずに、3回、取材に伺いましたが、
そのおかげで、夜通しの調査パトロールに複数回、同行させて頂き、
調査員の方や、後藤先生(84歳)にたくさんお話をお聞きでき、貴重な体験でした。
アカウミガメの保護に向けて、後藤先生、日本ウミガメ協議会の研究員、
大学で研究する学生さん、行政、そして地元の青年クラブの皆さん方が
千里の浜の調査や保全を、協力しておこなっていました


上陸したカメに標識をつける道具3種類
リュックに入れて、浜を歩く。
大きなノギス(甲長計測用)もかつぐと重く重労働です。

前脚の第2鱗板に装着する標識。
黄色は上陸や産卵した個体を示す。
青色は混獲された個体につけるそうです。
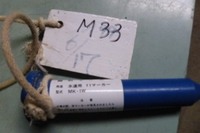
産卵した場所に埋める検知マーカー。
産卵日も記してある。
磁気で探知できる。
調査員の方たち(当時は4人)は2ヶ月近く泊り込みで調査を続けます。
取材に伺った際、青年クラブの人たちとのおそろいのタンクトップ(色違い)が到着。
ウミガメ保護レンジャーと、みんなでポーズをとって写真撮影しました!
けれど、ブログで公開はやめて! と言われたので、残念ながら。
調査地の本部に貼りますと言っておられたので、
今度の夏、また伺わせていただきます。
本州で一番、ウミガメ上陸数の密度が高いみなべ町の千里の浜です。
列車が通る以外は、本当に静かで真っ暗で、星が美しい浜です

2012年01月07日
65 ウミガメ育む千里の浜

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年10月10日掲載
アカウミガメが毎年産卵のため上陸する、貴重な砂浜 みなべ町の千里の浜。

海浜植物が生え、多様性に富む浜。
昨年の6月末~7月初めに3回訪れました。
しかし今年は上陸数が少なく、2回は空振り

徹夜を続けて、3度目の正直で、
ようやく出会えたアカウミガメに心から感動しました。
今まで水族館などで見たことはあっても、
野生のウミガメが遠い海から来た、ここで産卵しようとしている、
その場に一緒にいることが、とても貴重で、かけがえのない時間でした。

目をこらし、息ものんで、穴を掘る様子を、微動だにせず見守っていましたが、
結局産卵をあきらめ、戻っていくカメに、
産みたくても産めないのはしんどいだろうな。。
と自分の痛みのように感じました。
上陸しても半分は産卵できないそうです。
子孫を残すのは大変です。

産卵をあきらめて海に戻る。
再度、上陸する事もある。
相当のエネルギーを要します。
ウミガメの顔。

貝をわるくちばし、大きな頭。
観光客の人がライトを思わず照らした時、
ウミガメが逆方向に歩きはじめました。
研究員の方が注意を促しました。
ウミガメの生態に配慮し、そっと見守りたいですね。
調査パトロールの様子は次の記事でご紹介します。
2012年01月06日
64 こどもエコクラブで身近な自然観察

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年9月26日掲載
こどもエコクラブは環境活動をおこなう子どもたちとサポートする大人たちがいれば
だれでも無料で登録、参加できます。
1999年に地域の子供会単位で登録して以来、
細々とですが、活動を続けています!
子供会役員のお母さん方をはじめ、近所の方、生物の専門家など
いろいろな方にサポートいただき、
継続して、いろいろな年齢層の人たちと交流できるのが
エコクラブ活動の魅力です!!
今は公園の一角に畝を作り、大根と人参を育てています。
さてみんなで何を調理しよう。収穫も楽しみです。

この写真は昨年10月24日撮影。
今はもっと葉が大きく茂っています

2012年01月04日
63 1万羽を超すツバメのねぐら入り

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年9月19日掲載
繁殖を終えたツバメたちが、これだけの集団でねぐら入りすることは
知らない方も多いと思います。
日暮れ前後の30分で、あちこちからツバメが河川敷に集結してくる様子は圧巻でした。
空を見上げると、黒い雪が降ってくるがの如くでした!
ねぐらになる、アシ原の保全が求められます。
2012年01月03日
62 土に潜む希少なトタテグモ

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年8月29日掲載
取材よもやま話を参照ください。
クモを嫌う人は多くいらっしゃるようで、
ご近所のクリーニング店でいつも読んで感想をくださる方も、
クモは苦手で、、とおっしゃっていました。
編集でお世話になっている新聞社の担当記者の方からは、
コラムに添える写真候補に対し、
ビューティフルなクモの写真を!と、ご希望がありました。
私にとっては、クモはみなビューティフルに見えます

生態系の豊かさを示すクモ類に、ぜひ注目していただきたいです。
2012年01月02日
61 鵜匠の技術

クリックしてお読みください。
朝日新聞和歌山版2011年8月22日掲載
和歌山県有田川の鵜匠は、国内で唯一、
自らが野生の鵜を捕獲し、馴らします。
松明やタナオ(鵜の首につなぐヒモ)などの道具も
全て鵜匠が手作りします。

一回の鵜飼で燃えきる量の松明。
肥えた(油ののった)マツを自分で切り、束ねる。

タナオ
鵜の首につける輪は調節できるようになっている。

水浴びした後のウミウ。
間近で見た姿は、美しい光る黒い羽色で、
正面を向く両眼、4指につく大きな水かき、太く長い首!!
潜水して捕食する素晴らしい体型でした。
他の仕事の傍ら、鵜の調教、健康管理、道具の準備など
鵜匠の方々の手間は大変です。
長い歴史を継承する伝統を継承するためにも
この価値をアピールし、支援が必要と感じました