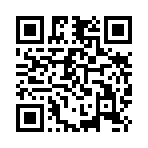2012年03月16日
80 太地町の博物館にいるクジラたち

朝日新聞和歌山版2012年2月27日掲載
前回に続き、太地町立くじらの博物館での話題です。
太地はくじらと共に歩んできた町。
この地で人と関わってきたクジラたちを知ってほしいと、
追い込み漁で捕るクジラ類を集め、
飼育や展示の工夫をしています。
ハナゴンドウ オキゴンドウ コビレゴンドウ
バンドウイルカ カマイルカ
そして、飼育下では珍しい マダライルカ スジイルカ。
大学などと連携して研究をおこなうと共に、
お客さんが間近で生態を実感できる場面も作っています。
クジラたちを近くで見れる桟橋

ハナゴンドウ

体の傷の模様からついた名前。
歯が少ない。 (記事のコビレゴンドウと比べてください!)
桐畑副館長さんのお話では、イカを多く食べるクジラは、歯が少ない傾向にあるそうです。
イルカやクジラのショーでは、
種類ごとの特徴や生態をきちんと説明し、
それにあわせた動き という教育的な構成でした。

バンドウイルカの鰭を説明。
野生のイルカは、ダルマザメに噛まれたり、
オスは闘争で傷ついていたりする。

ダルマザメが噛んだ跡(円い傷跡)が見えますか?
可愛い、癒される、というイメージが強いイルカたち。
本来、広い海で仲間とコミュニケーションを取り、
クジラたちはそれぞれのくらしを営んでいます。、
資源として、
ショーの立役者として
私たちと関わってきてくれた動物たちのことを
正しく知りたいと、豊富な資料が蓄積された博物館で思いました。
Posted by ポケット at 19:43│Comments(0)
│太地町立くじらの博物館