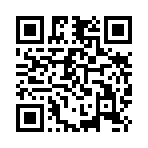2017年02月26日
104 紀州犬の展覧会

クリックしてお読みください
朝日新聞和歌山版2013年2月3日掲載
第77回紀州犬全国展覧会を取材しました。
愛らしい生後2ヶ月の姉妹が2頭、来ていましたが、耳を噛み合う恐れがあるとのことで、犬同士を近づけてはいませんでした。
狩猟犬としての闘争心を既にもっているのです。
審査では、ハンドラー(リードを引いている人)が、リードを斜めに持ち上げて犬を静止させます。
この時、うーと、唸りが手に伝わる感触が良いのだそうです

素朴さの中にある威厳。
渋いなあ、と、日本犬、紀州犬の魅力の奥深さを、親しみをもって感じました

2017年02月26日
103 紀州犬の育成

朝日新聞和歌山版 2013年1月27日掲載
クリックしてお読みください
和歌山の人が多く飼育する紀州犬。
紀州犬保存会審査員の方のお宅にお伺いしました。
気性が荒いイメージをもっていましたが、飼われていた犬たちは穏やかで落ち着いていました。
ブラッシングや散歩にかける時間や労力は大変なもの。
手をかけて育てているから、これだけの風格と面持ち と感じました。
大正時代から記録される系統図と和紙で作られた由緒ある血統書。
さすが天然記念物の日本犬。しっかりと血統管理がなされていました。
2017年02月26日
102 鳥の標識調査

朝日新聞和歌山版2013年1月20日掲載
クリックしてお読みください
バンディング調査の様子を見させて頂きました。
計測して標識をつけ放鳥する作業。
労力を要する大変な調査ですが、年齢や性別、季節ごとの野鳥の形態や分布状況を把握し、地道に少しずつ鳥たちの生態の解明につなげます。
2017年02月26日
101 ヘビへの畏怖

朝日新聞和歌山版 2013年1月13日掲載
クリックしてお読みください
巳年にちなみ、安珍と清姫の絵巻物語を演じている、道成寺に伺いました。
清姫が日高川をわたるときにヘビに姿を変える。。
実際にアオダイショウが水にどっぷりつかっている姿を、県立自然博物館で観察。
触るとすべすべで、足もないのにするする素早く強靭に動ける体のしくみ。
その姿や動きに昔の人も畏怖の念を頂き、伝説として語り継がれたヘビに、愛着を感じました

2017年02月26日
100 読者の皆さんの感想とこれから

朝日新聞和歌山版 2012年12月23日掲載
クリックしてお読みください
読者の皆さんから寄せられた感想で、一番多かったのが、熊楠邸での話題でした。
ほか、パンダの繁殖技術、ビルで子育てするハヤブサなど、和歌山ならではの動物の話題が好評でした

リクエスト頂いた話題も参考になりました。
読者の皆さんに心から感謝し、資源の掘り起こしと発信を、ご一緒にしていきたく思っています。
2017年02月26日
100 特集号 あなたの一押し記事は?


朝日新聞和歌山版 2012年11月9日掲載
クリックしてお読みください
編集担当記者さんが、100回を記念して、特集号を組んでくださいました。
読者の方から温かなお手紙や、取材リクエストも合わせていただきました

2017年02月26日
99 動物園は動物の生態を学ぶ場

朝日新聞和歌山版2012年10月14日掲載
私の恩師、中川志郎さんのご逝去は、大変辛く悲しい出来事でした。
1970年代に中川先生が書かれた動物園学ことはじめには、動物園の社会的役割に、自然保護に貢献する教育の重要性を示しておられます。
レクリエーションも、動物への愛情、動物福祉があってこその、人間性の創造(re-creation)。
動物園の動物たちは「野生からの大使」
動物たちのメッセージを読み取ることが、私たちの責任だと思っています。
2017年02月26日
98 熊楠邸のカメの小太郎

朝日新聞和歌山版 2012年10月7日
クリックしてお読みください
熊楠の長女の文枝さんが、大事に育て、熊楠邸で唯一生き残っている、クサガメの小太郎。
熊楠や家族が実際にカメを育てた泉水で、小太郎に対面できた嬉しさは一塩でした。
実は取材で行っても小太郎はなかなか姿を見せず
 、3度目でようやく会うことができました。
、3度目でようやく会うことができました。真っ黒でつぶらな瞳。
熊楠は息子の熊弥を喜ばそうと、カメを手に入れ見せていました。
熊弥のカメに対する反応が日記に詳細に書かれているのを読み、熊楠の我が子を思う愛情に、感動して思わず涙が出ました

2017年02月26日
97 熊楠が飼った動物たち

朝日新聞和歌山版 2012年9月30日掲載
クリックしてお読みください
熊楠邸(田辺市)に伺い、熊楠が飼っていた動物について、遠戚で案内役の橋本様にお話をお聞きしました。
ネコの名前はみんなチョボ六。
カメは成長段階ごとに分けて泉水に入れて飼っていたとのこと。
いろいろな動物と、訪れるたくさんの人たちに囲まれて、晩年をすごした旧邸での熊楠のくらしは賑やかで穏やかだったのではと思いました